SUGAI KEN:環境音と電子音の円熟サウンドスケッチ

フィールドレコーディングをめぐる地平は近年さらなる広がりを見せている。文化人類学的見地からの“記録”としてのそれから、急増するASMRや睡眠用BGMなどの日常的な活用−−これはもう一種の“娯楽”と呼んでいいだろう−−まで、さまざまなかたちでフィールドレコーディングの有用は実践されている。もちろん現代の音楽シーンにおいてもその存在感は拡張している。高品位なマイクやレコーダーの普及により、誰もが環境音を手軽に録音できるいま、アーティストたちはどのように音を採取し、独自性を獲得したのだろうか。
本稿では、日本の電子音楽家であるSUGAI KENの制作スタイルや音楽的バックボーンをもとにフィールドレコーディングにおける矜持を探る。SUGAIは2010年発表のファーストアルバム『時子音 - ToKiShiNe』以来、日本的な叙情性を環境音と電子音によって表現し続けている。2016年にメルボルンのLullabies For Insomniacsから『鯰上 - On The Quakefish』を、2017年にはニューヨークのRVNG Intl.から『UkabazUmorezU』を発表、国外名門レーベルからのリリースで世界的にも注目が集まる彼の近作から、独自の哲学と手法を紐解く。
2020年以降に発表した2作品、『Tone River』と『必ず喫茶時にお聴き下さい。』は彼が模索してきた日本の風土/伝統文化と電子音楽のフュージョンとして、現時点での最新研究報告である。前者は、新潟県南魚沼の大水上山を水源として関東を横断、そのまま太平洋へと流れ込む国内三大河川のひとつである利根川をモチーフにした2020年のアルバム。後者は京都は山城にて150年以上の歴史を持つ老舗茶問屋、宇治香園の音楽プロジェクト“Tealightsound”の一環として、廃茶園などで録音された環境音を取り入れた2021年の作品。このふたつのアルバムを題目として、フィールドレコーディングで採取した音をどのように作品に昇華させるかの手ほどきを、そして彼の音楽性の背後に横たわる日本文化への思いを訊く。

山中の茶園脇で水中音を採音している様子。
まず、2020年に制作された『Tone River』の制作において中心的な役割を果たしたと思う機材やプラグインについて教えてください。また、その機材/プラグインはどんな効果を期待して使用したのかについても教えていただければ。
環境音の収録にはバイノーラル・マイクロフォンとハイドロフォンを使用しました。前者は環境音における臨場感を、後者は水中感が出ることを期待して使いました。バイノーラル・マイクロフォンでは比較的角度の広い録音ができたのではないかなと思います。マイクの使い方については普通だと思います。あまり変則的な使い方はしていません。工程というほどのものはないのですが、強いて言うならばマイクをセットしたあと、録音中に自分がその場に留まるケースと離れるケースがあります。音にたいした違いはないのかもしれませんが、自分がその場から離れることによって、その場のより自然な気配が録れる気もしています。なお、ほとんどのフィールドレコーディング音源は録音者が息を潜めて存在を極力消す風潮にありますが、よく考えてみるとそれは不自然なようにも感じられるため、“Symphonic "Joya no Kane””では、わざと途中でマイクを触ったりしてみました。
どんな音を聞いたときに採音しようと思うのでしょうか?
思い付くものとしてはふたつあります。ひとつ目は作品のコンセプトに沿う音です。『Tone River』では、文字通り“川”にまつわるものをレーベル側から求められたため、録音しました。ふたつ目は個人的に惹かれる音です。生活感や地域性を感じられる音のほかに、怒号や罵声や嘘など人間の欲望が滲み出た音も今後は録音したいです。事後の低音処理で不要な通低音を削るケースが多いです。ただし、一様にすべてカットすると不自然な場合はダイナミックEQなどで必要箇所のみ残すようにしています。
過去の本作にまつわるインタビューにおいて、「~1曲目(“坂東太郎のはぢまり”)の冒頭には声をノイジーに加工したものが入っているんです」との発言がありましたが、その際の加工工程を教えていただければ。
声の加工にはビットクラッシャーを使用しています。利根川の源流が環境汚染の影響を受けていて、その“汚染”をこのエフェクト特有のザラつきで表現しました。 個人的な意見ですが、ほかのノイズ系エフェクトよりもビットクラッシャーのほうが”汚染”的な雑味を表せるかと思っています。ほかに例を挙げるなら、5曲目の“坂東太郎のあらまし”において、2分13秒あたりの轟音については複数の周波数帯を組み合わせたことによりおもしろい鳴りになった気がしています。3~4層の周波数帯の通底音を重ねたと思うのですが、干渉縞のような独特の音のうなりが印象的でした。
『Tone River』制作におけるフィールドレコーディングについて、音源に使用してない部分も含め、どのくらいの録音時間があったのでしょうか? そして録音した素材のどの部分を切り取るか、SUGAIさんが思うフックはどこにあったのかについても具体的に教えていただければ。
覚えている範囲で恐縮ですが、各録音場所でそれぞれ10分前後、トータルで録音時間は20〜30分だったと思います。環境音録音のために1日で約600kmを車移動したのは初めてで、体力的にとてもキツかったですね。音源の使用箇所については、なるべく音に急激なピークがない箇所を選択しました。 ピーク部を使用してしまうと、ヘッドルームの確保に苦労しそうな予感がしたためです。環境音に関しては変にコンプでつぶしたくないと思い、かつ自然に音量を稼ぐためにもヘッドルームを意識した次第です。
本作において、フィールドレコーディング素材を楽曲として落とし込む際の制作工程はどのようなものだったでしょうか?
この作品に関しては環境音と曲を別で考えていたので、厳密に言えば環境音が揃うまえから曲は作り始めていた気がします。この作品の意義のひとつでもある“記録”もしくは“無作為”という点と、曲を作るという作為的な行為をひとつの作品にまとめるには、別にしたほうがよいと思ったからです。後者の楽曲制作のプロセスについては環境音録音以前ということもあり、まだ現地へ足を運んでいない状況のなか、利根川の治水の歴史などさまざまな事柄を調べるうちに湧きあがってきたイメージを曲作りに落とし込んでいきました。
『Tone River』の制作ではマイク以外に、音の暖かさを出すためにアナログ・シンセサイザーを使用し、冴えた音の響きを期待してデジタル・シンセサイザーを使用しています。また、音の表面を滲ませるためにトランジスタ・サチュレーターを使い、音像に柔らかい陰影を付加するためにアナログ・エコーを使っています。そのほか、ボコーダーで声を電化させたり、独特の揺れを加えるためにオープンリールのテープを通すなどしています。
本作における音素材の配置や音響空間の構築についてどのような配慮がありましたか?
近年のぼくの作品においても顕著ですが、音響空間構築や素材配置を行う際はなるべく自分の心象風景に忠実に配置するよう心がけています。抽象的な表現ではありますが、心象風景を視覚的に捉えた際に、その“画”をいかに音で表せるかという点です。たとえば、”画”の左側に硬いイメージがあれば硬い音を配置、右側に柔らかいイメージがあれば柔らかい音を配置といった感じです。各個人によってその感覚は千差万別ですので、これに関してはおそらく正解も不正解もないとは思うのですが。
SUGAI KEN “瑞泉”。SUGAI KENの諸作品で多用されているモチーフ音が、冒頭から22秒までに使われている。
そういった”軸"となる部分の純度を下げて世間師になってしまうと、好ましくない結果につながることが多くあるように思います。ただし、作り進めるうちに自分の対外的な“色”を付けたいという欲求……それは垢とも言い換えができますが、そういったものも芽生えてきますので、その場合は“外装塗装”をするケースもあります。2010年の作品からずっと意図的に使い続けているモチーフ的な音があって、これは木造文化の日本において、日本人が無意識に懐かしさを覚えることが実証されている音の成分なんです。その成分は言語学の分野にも関係していて、欧米などの石造文化圏では敬遠される傾向にあるそうです。外装塗装というのは、そのモチーフ的な音を使ったり、いわゆるSUGAI KENのイメージとして持たれているようなメロディーを加えたりなどです。これは意図的に特色へつなげる行為のような感じとも言えます。

蛭(ヒル)や虻(アブ)に注意しつつ、水中音を採音している様子。
続いて、2021年に発表された『必ず喫茶時にお聴き下さい。』がどのようにして作られたか、どのような音響を目指して制作されたかについて教えてください。
本作は京都の宇治香園から制作のご依頼をいただきスタートした作品になります。なかでも本作5曲目の“ちゃ_と_気配”は比較的イメージに近いものができた気がします。 この“ちゃ_と_気配”では、“楽曲”然としてしまうと作為的すぎてイメージと合わなくなってしまい、純度が落ちるような気もしたので、なるべく自分が思い描く気配を音で表した次第です。個人的にはお茶を“清廉潔白な癒し”で括ってしまうことにどこか浅はかさを感じてしまい、もう一歩踏み込んだ表現として、漂う気配としての狂気を表したいと思いました。ちなみに煎茶からは話が逸れますが、いつ自分が命を落とすかわからないという心境であった戦国武将が特濃の抹茶でトリップして戦に向かったというエピソードを何かで読んで衝撃を受けたことがあります。そういった”エグい”癒しという側面のほうが個人的には惹かれます。
1曲目“夜明けの山林に響く謎声を電子音で再現”で実際にある自然音を電子音で再現するにあたり、どのような苦慮があったのでしょうか? また、その際の制作工程についても具体的に教えていただければ。
当たり前のことですが、自然音はとても有機的です。分析するとパターンがあるようで実はないケースも多くあり、その逆も然りです。そのため、単純に制作で時間がかかります。制作工程はすべて人力で行い、何度も元音を聞いてアナログ波形で近づけていきます。その際、DAWで波形を拡大するなど、視覚的にも確認しています。 なお、野外の残響感を表すために野外で収録されたインパルス・レスポンス(IR)のデータを該当音へ使用してもいます。具体的なプロセスとしては、現地環境音のなかで聞こえる鳴き声を分析して、別途、鳴き声だけを電子音で再現します。それから、IRデータをリバーブにインポートして、再現した鳴き声にかけ、現地環境音の鳴き声のない箇所とミックスしています。“夜明けの山林に響く謎声を電子音で再現”では実際の現地環境音を使用して、鳴き声のみ電子音で制作してミックスしています。
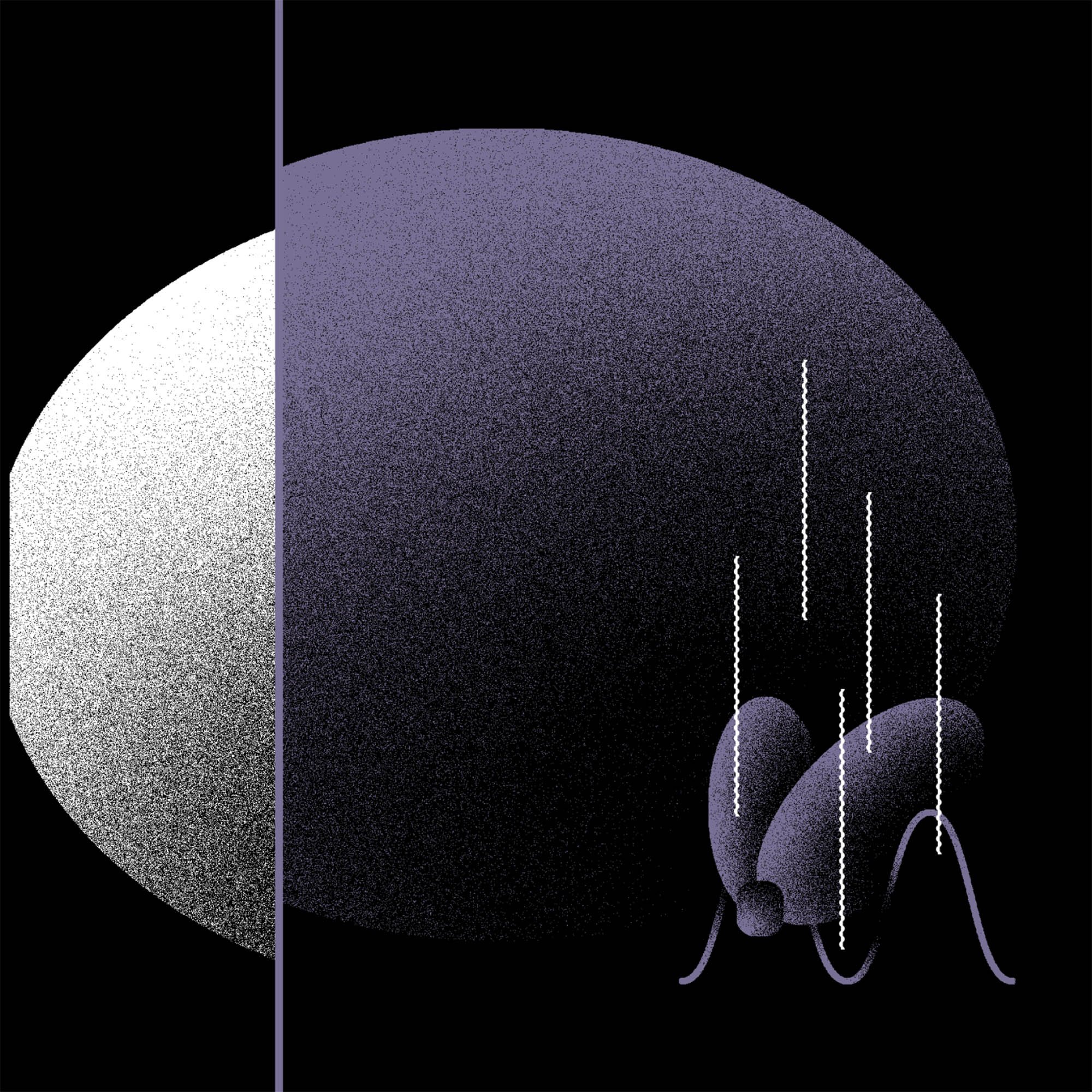
SUGAI KENが虫の音を電子音のみで再現して高い評価を獲得したアルバム『如の夜庭』。
今回ご提供していただいたフィールドレコーディング音源はどこで、どのように録音された素材でしょうか? また、音源の聞きどころはどのような点ですか?
自宅近くの野川、サイクリングロードの休憩場、ショッピングモールや図書館にて、バイノーラル・マイクロフォンとハイドロフォンを使用して録音しました。聞きどころはサイクリングロード休憩場で不意にあらわれた男性ランナーの下品な口濯ぎ音です。
SUGAIさんの制作では、音響効果において音と無音の“間”が非常に効果的に用いられています。こういった無音の時間や“間”のタイミングについてどのような配慮があるのか教えてください。
すべてではありませんが、いまだに音楽を含めたトレンドの発信源は欧米であることが多いと感じます。 欧米の基本原理は動物的なものが多く、反発/征服原理に基づいたものが多いように自分は感じていて、メディア上でも数で圧する……DAW上では”音で圧する”ような……光景を多く目にします。もちろん、これは欧米文化を否定するものではありません。それに対してアジア圏は相対的に植物的な文化が多く、同化原理に基づいた考えが根底にある気がしています。ただ、近代の欧米化によりかなり動物的になってしまっているとも感じますが、このまま欧米の方法論に乗ってしまうといつまでも二次的になってしまうと昔から感じていたため、試行錯誤しながら現在に至る、といった感じです。ですが、まだまだ理想とは程遠い状態です。個人的には、とくにライブパフォーマンスで音と無音がお互いに補完しあう関係性の構築を目指しています。そういった考えの根幹には『風姿花伝』*という日本の文献を読んだ経験も大きく影響していると思います。
*風姿花伝:室町時代初期に活躍した猿楽師である世阿弥が、自らが会得した芸術論について記した伝書。能楽はもとより、日本のさまざまな芸術の礎ともなった国内最古の演劇論書である。
SUGAI KENというアーティストを評するにあたって“日本的である”といったことが多く言われていますが、そういったイメージやジャポニズムという観点についてSUGAIさん自身が思うところがあればお伺いしたいと思っています。また、和楽器などの記号的な音を用いずに日本的な音楽を表現するための工夫があれば併せて教えてください。
ぼくの作品が日本的であるかどうかは聞く方々の判断に委ねます。「日本的な音楽を表現するための工夫」についても、毎度、苦慮しています。根拠は明確にしつつ、ある程度“軽薄”な創作を愉しむように心がけています。ジャポニズムという論点とはずれてしまうかもしれませんが、日本文化について2点申し上げます。
1点目は“渋い”という通念がとても重要だということ。“WABISABI”は、ぼくら日本人の日常ではあまり見かけず、いまや輸出用の標語のような存在ですが、“渋い”という言葉はいまでも日常会話に多く出てきます。この貴重な通念の価値を我々日本人はいま一度見つめ直すべきなのかもしれません。“WABISABI”という言葉はパロディーとしては有用であるようにも思いますが、日本語での“侘び寂び”は重要な概念だと思っています。“侘び”は清貧という言葉と近い気がしていますが、自分の勝手な解釈では、権威的なものや流行りものを通過し、飽きた際に、質素なものやボロボロなもののなかにさらなる高次元な世界を発見してしまった変態性であると思っています。思い通りにいかない現実を逆に愉しんでやれというたくましさも内包している気がします。“寂び”は万物はやがて古くなるという摂理や無常観を慈しむことだと解釈しています。そもそも人生は若くない時間のほうが長いのに、ユースカルチャーへの依存度がいまだに現代日本は高すぎるなと感じています。30歳前後を境にして文化的創造から卒業してしまうケースを多く目の当たりにしてきました。これは日本の悪しき慣習である長時間労働も無縁ではないと思いますが。一方で、“日本が世界に誇る~”と銘打たれる文化の多くは“渋い”ものではないでしょうか? そして、その多くはかつての先人が老境で咲かせた”花”により一層深化したように感じます。もちろん単に時間をかければいいという話ではありませんが、一朝一夕では成し得ない、熟成し高濃度となった狂気的な表現が巷に溢れることを願っています。高純度な“老エクスタシー”や“枯れた狂気”に期待をしています。
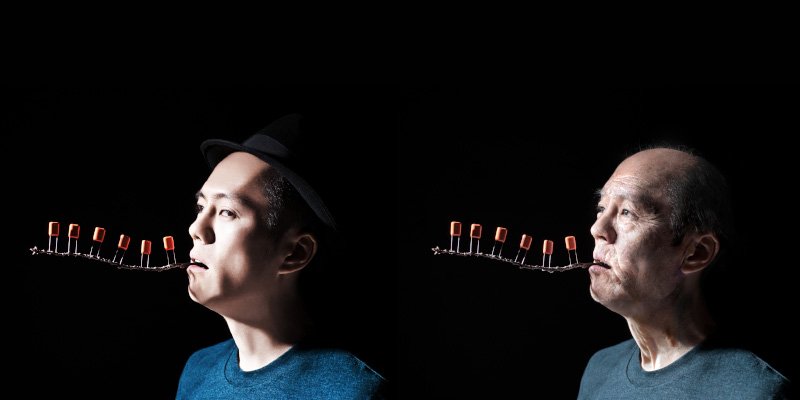
左は、アーティスト写真で空也上人をパロディー化したSUGAI KEN(2012年)。右では、“窶し(やつし)”という日本の高度な美的感覚にそって自身を老人化させている(2020年)。
2点目はまだまだ珍妙な旨味を我々日本人は知らないということです。例としていくつか動画を挙げます。
この動画にはありませんが、見えざる田の神へのもてなしとして主人が全裸になっていっしょにエア入浴もするそうです。
観覧している子供たちの微妙な表情も含め、サイコーさしかありません。
シュールさがたまりません。
読者のみなさんも、ぜひ足元に眠るエクストリームな民俗文化をディグし、ご自身の創造へと昇華させてください。 伝説の田楽師である一忠や天才作庭家の延円をはじめ、柳宗悦を導いた大川亮、大正時代にすでに音を色で捉えていた鈴木鼓村、「ひとの動きや生活には一定のリズムがあり……」とMurray Schaferばりの抽象度で“リヅム”を周期として捉えていた飯沼一雄など、果てない偉人たちがあなたを待ち構えているはずです。
SUGAI KENのフィールドレコーディングをダウンロードする
文/インタビュー:Keita Takahashi
写真提供:SUGAI KEN
SUGAI KENの最新情報をフォローしよう:Linktree