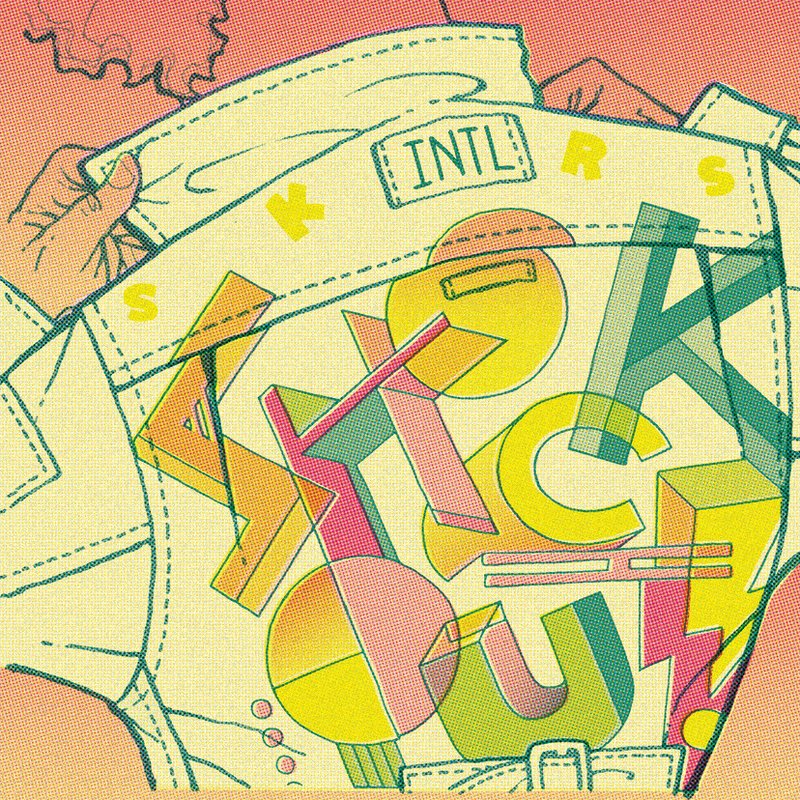Seekersinternational:アブストラクト・ダブ・サウンドシステム

正体をはっきりと明かそうとしないSeekersinternationalについてわかっていることと言えば、ブリティッシュ・コロンビア州のリッチモンドを拠点にするフィリピン系移民と第1世代フィリピン系カナダ人がメンバーで、メトロ・マニラ(マニラと周辺地域で構成されるフィリピンの首都圏)と強いつながりを持っていることくらいだ。彼らの出自や居場所は定かではないにしても、ここ5~7年間にSeekersinternational(SKRSINTLやSKRSと記載されることもある)名義で生み落とされてきた音楽が、サンプリングを基調にしたダブ的アプローチによる斬新な音楽制作を提示しているのは確かな事実だ。
1970年代のジャマイカにおけるスタジオの技巧とサウンドシステム・カルチャーをルーツとするダブ・ミュージックの誕生から数十年。その間に膨大な数の変異形が現れた。レゲエの確立されたスタイルに則ったものがあれば、ダブをつうじて既存の枠組みを超えたサウンドを模索するものもある。しかし、Seekersinternationalのダブを独特なものにしている(そして、独特な面白さを生み出している)のは、この両方のアプローチを何らかのかたちで両立させている点だと言える。それを支えるのは必ずしもメロディではなく、うまい表現が見つからないのだが、ときに濃密でときに削ぎ落とした彼らのサンプリング・コラージュが生み出す“キャッチーさ”とフロウだと言える。この点について彼らは「SKRSの肝である音選びが別次元のダンスに導いてくれる」と語っている。
Seekersinternationalの広報役を担当するDaddy Coolbreezeと行った今回のインタビューでは、90年代のターンテーブリズムやビジュアル・アートといった彼らのルーツのほか、Ableton Liveで使用するサンプリング音源の探し方と研ぎ澄ませ方、相反する要素をダブで解消していることなど、多くのトピックについて話を聞いた。さらに、彼らは独自のレーザー・サウンド・エフェクトやサイレンといった音源を収録したPackも制作してくれた。インタビュー内のリンクから無料でダウンロード可能だ。
Seekersinternationalはいつどこで始まったんですか?
僕らは、90年代半ばから後半にかけてのDJ/ターンテーブリスト・カルチャーから派生して結成したんだ。もちろん、その時期に影響を受けたアートのムーブメントはたくさんあったけど、とくにDJとターンテーブリズムは僕らに新しい世界を切り開いてくれた。レコードからサンプリングした音をつなぎ合わせて新しいオリジナルの曲を作れるという意味でね。あれはかなりの衝撃だった。音楽教育や楽器とかの制作機材に縁が無かったからさ。
同じくらい、というか、それよりも大事なのは、ターンテーブリストのムーブメントをリードしていたのが、ベイエリアのフィリピン系アメリカ人だったこと。 DJ Q-bert、Mixmaster Mike、Shortkut、DJ Disk、DJ Apolloとかね。その人たちが、僕らみたいな移民少数派の多くにスタイルや意思を示したんだ。ものすごく勇気づけられたよ。総じて言えば、ターンテーブリズムが全く新しいエネルギーと視点を僕らに与えてくれて、自分たちだけのアーティスト表現を築き上げるように後押ししたんだ。
それと同時に、ジャマイカのダブ・ミュージックやサウンドシステムのカルチャーとの出会いは、Seekersinternational全体の方向性を決める重要な出来事だった。一見全く異なるふたつのカルチャーだけど、実はたくさんの共通点がある。もっとも顕著なのは、自分のやり方で創造性を見い出そうとするDIYな姿勢。自分の持っているものから最良の結果を生み出して、限られた環境から最大限の結果を引き出すんだ。それに、ジャマイカ音楽の基本にある“みんなのために”っていうバイブスにみんながハマった。偉ぶっていなくて人を選ぶ感じじゃないし、重みのあるとんでもなく最高のバイブスが詰まっているんだ。
ダブで大事なのはドラムとベースだけっていう古いやり方を変えたいんだ。
『The Call From Below』や『TheWhereBetweenYou&Me』といったSeekersinternationalの初期のリリースは、そうした時代よりも後の90年代にBasic ChannelやRhythm & Soundのようなアーティストが発展させたダブのスタイルから影響を受けているように思います。初期のトラックだとドラム・サウンドを大きく取り除いて、音の隙間をコードやベースで埋めているところも似ていますし、ヒスノイズ、音割れ、コンプレッサーによる思わぬ効果など、偶発的なサウンドで作られたかすれた空気が、さらにトラックを際立てています。Seekersinternationalも彼らの系統に属していると思いますか?
Burial Mix、Rhythm & Sound、Basic Channelの全作品は、間違いなく衝撃だった。ダブ自体の革新にとらわれなくてもいいってことを示してくれたからね。彼らが登場するまでのダブは、レゲエミュージックの中だけで作り変えていて、特定のテンプレートやフォーマットに陥っているような状態だった。もちろん、ディスコやポップスの12インチシングルみたいに、違うジャンルでダブを取り入れた音はあったけど、彼らみたいにダブの世界観やアプローチを真摯に探究したものではなかった。それをBasic Channelの人たちが覆したんだ。
僕らの制作では、通常のドラムのビートを取り除くシンプルな行為がとても重要なんだ。またBasic Channelの話になるけど、僕らが初めて彼らのサウンドを浴びたのは、太平洋側の北西部でありがちな野外レイブだった(笑)。遠くから大音量でBurial Mixのトラックが流れてくるのを聞いたんだ。そのリディムに聞き入ったね。遠くからだとハイハットやスネアの高域の周波数がほぼ完全に消え去って、聞こえるのは力強く迫ってくる巨大な鼓動とリディムだけなんだけど、心地よくて自然そのものから発せられているみたいだった。シンプルで神々しかった。ドラッグのおかげであの体験ができた可能性は多いにあるけど、僕らが受けた衝撃はそれ以来ずっと創作活動のDNAの中に深く染み込んでいる。
その時の体験で僕らの中の理解が深まったんだ。どの音楽にも勢いを支える隠れた鼓動が存在していて、その鼓動は、常識とは違ってドラムやベースのようなものに依存しなくても存在できるんだってね。その暗黙の鼓動をドラムは“言語化”しているというか、装飾しているだけで、鼓動そのものを必ずしも生み出しているわけじゃない。たいてい僕らにとってドラムを抜くというのは、その秘められたものを認識して大事にする行為なんだ。ダブ・ミュージックでしょっちゅう話題になる神々しい瞬間や感覚っていうのは、ボーカルや他の要素が急にディレイで飛ばされて、残されたドラムとベースだけでグルーヴが保たれているときのものだけど、それと同じ感覚はドラムやベースラインが無くなっても味わえるんだ。フッと浮いている感じになっても、しっかりとグルーヴにハマっている状態でね。僕らは、ダブで大事なのはドラムとベースだけっていう古い作法を変えたいと思っているんだ。
いずれにせよ、音楽全体を聞いてもいないのに、1小節目のビートとドラム・パターンだけで音楽を判断して、ラベルを付けて分類する傾向があると思う。「ああ、これはレゲエ・スタイルのリムショットだ」「これはハウス・スタイルの4つ打ちキックとハットだ」「808の音だからトラップだ」とかね。ひどい場合だと「コンガの音だからワールド・ミュージックだ」みたいな。もっと言えば「ドラムが無いからアンビエントだ!」ってね。ドラムの強力な効果を否定するつもりは全くない。僕らは、ドラムに意識を独占されずにそうした音の印象を改めて伝えられるのか試したいだけ。とは言っても、僕らもトラックでドラムを使うよ。でも、すごく意図的にやっていると思ってくれていい。
Seekersinternationalの作品を聞き返すと、サンプリング音源を操作する方向に進んでいるような印象を受けました。とくに、ボーカル・サンプルをワンショットで刻むのではなく、トラックの中心的モチーフとして使う方法を推し進めている気がします。この方向性は意図的に決めたことだったんでしょうか? サンプリングの音はどこで手に入れていますか? あと、サンプリングする音を探すときは何に注意を向けていますか?
ターンテーブリズムの出身だから、サンプリングは僕らのやっていることの中心にある。僕らがスクラッチDJのミックステープやDJバトルの黄金期だと考えている時代には、フレーズ、小節、旋律といった要素を全体的に聞いて、スクラッチ、編集、ループ、コラージュなどの操作でどうなふうに濃密で独特な作品に変化しているのかをチェックするのが普通だった。その好例が、Mixmaster Mikeの名作『Mixmasterpiece』や『Explosive Box Cassette』だ。浴びせるような大量のカッティングとサンプリングが常に盛り込まれていて、熱狂的な音のコラージュを作っている。村上作品のオーディオ版みたいな感じかな。そういうのを基準にすると、僕らの使うボーカル・サンプルは比較的控えめでミニマルなんだよ。だからそうだね、サンプリングに傾倒するようになっているのは意識的なことだ。でも、いわば僕らのルーツに戻っているというか、立ち返っているっていう方が近い。
若いときに憧れたヒーローに倣って、僕らも本当にあらゆるところからサンプリングしている。レコード、テープ、フィールド・レコーディング、電話の録音、テレビ、ビデオ、YouTube、ライブ、アナログ、デジタル。僕らにとっては、どれも同等なんだ。キーボードやシンセとか楽器の音をトラックに加えるときですら、トラック上で実際に演奏しているというよりも、サンプリングしているのに近いと思っている。もちろん仕上がりは結構違うけど、作品を構築するときの僕らの心構えやアプローチの表れになっている。
注意して聞いているのは主に音の特徴的な感触だね。ボーカル・サンプルに関して言えば、サンプリングする音源の音声そのものや意味よりも、音の感触や文脈を大事にしている。たとえば「murder」って言葉を探しているとして、夜のニュースでその言葉が使われている部分をサンプリングするのと、ダンスで「musical murda!」ってトースティングしているサウンドシステムのディージェイをサンプリングするのとでは全く違う。感触、そしてその感触がもたらすバイブスが全く違うんだよ。
アレンジに取り掛かって、たとえばボーカル・サンプルをレイヤーにまとめるのは、主要な役割と補助的な役割を果たすサンプルをどれにするのかを決める作業なんだ。バンドやオーケストラで楽器の役割を決めたり、絵画で使う色や、演劇で俳優を決めたりするのと同じだ。たとえば『Undercover Lovers』もそうだったんだけど、90年代前半のR&Bの曲を見つけて、AメロかBメロの歌詞から「undercover」「lovers」「girl」っていう部分をチョップしたんだ。それをメインのループにして他のサンプルを周りに乗せていった。
もうひとつ際立っていることとして、サンプリングしたとわかる状態のままサンプルが使われていることが挙げられます。ピッチの変更、チョップ、短い繰り返し、ストレッチといった操作がサンプルの実体を強調するかたちで行われています。そういう操作のほとんどにLiveを使っているんでしょうか?
何かわかるように明確にしたサンプルもあるけど、正体がわからないようにするサンプルもある。そういうときは、どれがサンプルでどれが“演奏”なのかリスナーがはっきりとわからない、もしくは気にならない程度にしているかな。でもそうだね、サンプルをサンプルだって強調するときは、サンプリングという過程/芸術/行為そのものに敬意と賛成の意を示しているんだ。それに、特定のサウンドを聞いてリスナーが連想するものや記憶についても考えている。
これは大事だと思うんだけど、僕らの中心メンバーには、DJを始める前からビジュアル・アートのしっかりとした経歴があるんだ。そのことが僕らの音楽と制作に対するアプローチを物語っている。僕らは音楽教育を受けていないし、機材に詳しいわけでもないからね。たとえば、僕らにとってサンプルを使ってトラック制作をするのは、画像の断片を使ってコラージュ作品を作る行為に直結している。僕らのLiveの捉え方や使い方は、素材に手を加えながら作品を仕上げるアートボードのそれと似ているんだ。Liveのレイアウトやデザインは、どこか僕らのビジュアル感覚に訴えるものがあって、おかしいかもしれないけど、Photoshopのようなビジュアル・ソフトを連想させるんだ。そうすることで、Liveの画面を理解して操作することが簡単になる。
メンバーごとに違うフレーズやアイデアから制作を始めることもあって、それがサンプルなのか、ベースのリフなのか、ドラム・パターンなのかはわからないけど、最終的にLiveにすべて入れて仕上げている。かなり前のクラシックなシンセやサンプラーを使うのも楽しいけど、デジタル環境の個性や特性、そして言うまでもなく効率性も同じように大事にしているよ。だからLiveは、すべての素材をまとめる場所として使って、ラフなアイデアを試したり、完成形の微調整を行ったりしている。
製品の宣伝っぽく聞こえてたら、すみません(笑)。でも、言っていることは本当で、僕らみたいなちゃんとした音楽的じゃない人にもしっかりと対応してくれる。視覚的にアプローチできるからね。そこは強調しておきたい。音楽的じゃない人たちが使う気になってくれたらうれしいね。
Seekersinternationalの最新作『Black Mazda Soundclash』。ダンスホールの空気をアブストラクトに表現した強烈なミックスだ。
普段、トラックやアルバムの構成はどのように考えていますか?
技術的なことを言えば、ほぼ間違いなくアレンジメントビューを使っている。繰り返しになるけど、その方が視覚的に僕らの好みに近いんだ。すべての演奏はコンピュータの外でやりたいと思っているんだ。シンセ、ドラム・マシン、サンプラーとかね。まず、そうした機材の音を素材としてLiveにすべて録音する。それから、カット、エディット、音作りといった全部の作業をアレンジメントビューでやっている。外部のエフェクトをかけた状態でトラックに録音することが多い。その意味で音作りはすでに行っていることになるけど、センドアウトをリバーブやディレイにアサインすることも結構あるよ。
機材オタクじゃないし、技術に詳しいわけでもないんだ。アナログシンセ、エフェクト、テープ・マシンがいい感じにそろっているけど、豪華なものじゃないし、機材に夢中であるわけでもない。Roland Space EchoやMoogerfoogerとか、ありがちなエフェクトを使っている。アナログのモノシンセも結構使っているよ。たとえば『Dancehall Showdown』のトラック・パートは、ほぼKorgのMS-20だけで作った。
サンプリングや録音した音を同期させたり、MIDIクロックで合わせたりすることはあまりなくて、Liveのタイム・ストレッチ機能を結構使っている。作業の大半は、素材をきれいにまとめることに費やしているんだ。だから、押したり引いたりしながら、我慢強く試行錯誤の作業だね。そうすることで、意図しているときも、そうじゃないときも、一種のゆるさと粗さ、それにファンクな要素を保つことができる。
実を言うと、最後のミックスダウンに至るまでの全作業をアレンジメントビューでやっているんだ。アルバムやミックス(『Dancehall Showdown』『Gunman Cult Classixx Mix』『Black Mazda Soundclash』など)みたいな長い尺で作品を作り始めると、 すべてのトラックを重ねてひとつの大きな作品にするから、とんでもない量のサンプルを同時に扱うことになる。それをセッションビューでやろうとすると考えるだけで、気が狂ってしまうよ!
最後になりましたが、サンプリング音源のPackを制作/提供してくれてありがとうございます。Packについて教えてもらえますか?
制作したPackは『SKRS SHØCKOUT PΔCK』という名前で、中には15種類の独特なレーザー・サウンド・エフェクトが入っている。制作やサウンドシステムのイベントで自由に使ってほしい。音作りには、Sequential CircuitsのPro-Oneだけを使ったんだ。Pro-Oneのとんがったモノフォニック・サウンドを大量に録音した。そのうちのいくつかをレイヤーにして、Liveの内蔵エフェクトで深みのある複雑な波形にしている。装飾音に使ってもいいし、サウンドシステムで盛り上げるときにも使えるよ。
画像提供:Mysteryforms
Seekersinternationalをフォロー:Soundcloud|Bandcamp|Twitter